年代・学歴別製造業の平均年収!メリット・デメリットやおすすめの資格もあわせて紹介!
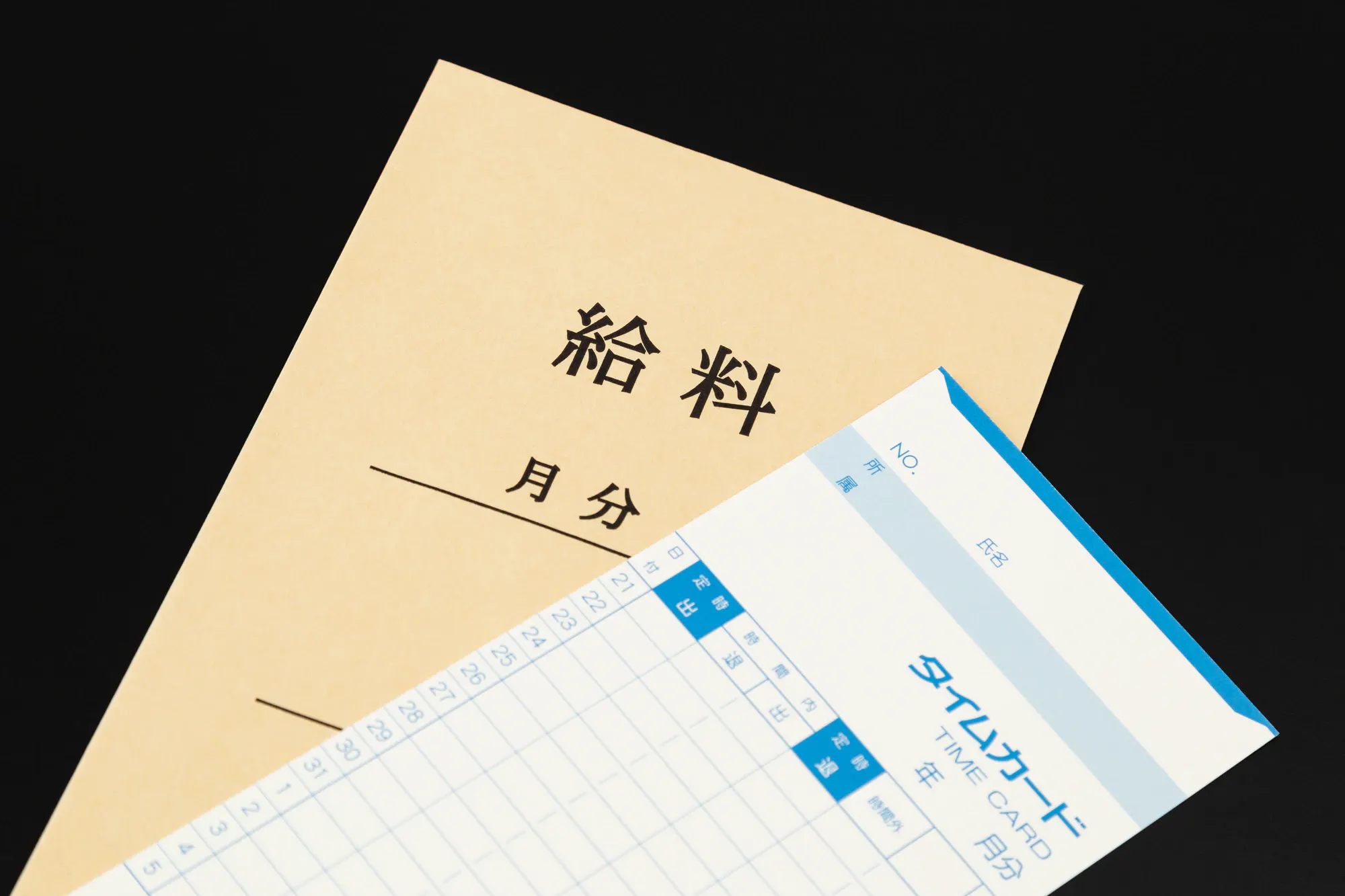
これから製造業に従事したいと考えている人であれば、「どのくらい稼げるのだろう」と、気になっているのではないでしょうか。
「製造業に興味がある」「ものづくりが好き」など、働きたいと思ったきっかけはいろいろであっても、あまりに収入が低いと仕事のモチベーションも上がりませんよね。
そこでこの記事では、製造業の平均年収や、学歴や雇用形態による年収の違いを紹介します。
製造業で年収を上げる方法や、優遇される資格も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
製造業の種類

製造業には、さまざまな職種があります。
まずは、製造業にどのような仕事があるのかを確認していきましょう。
- 食品関連
- 木材・木製品関連
- 機械関連
- 金属・鉄鋼関連
- 化学関連
- 建築関連
- 医薬品関連
- 電子部品関連 など
原材料を加工して製品を作る仕事は、基本的に製造業に分類されます。
ですから一言で製造業と言っても、多種多様な分野があることを覚えておきましょう。
製造業の平均年収

国税庁の「平成30年分民間給与実態統計調査」によれば、製造業の平均年収は約519万円です。
この調査結果を基に、年代・業種別に年収を確認していきましょう。
年代別の平均年収
年代別に比較した製造業の平均年収は以下の通りです。
~19歳 | 約274万円 |
20~24歳 | 約327万円 |
25~29歳 | 約410万円 |
30~34歳 | 約462万円 |
35~39歳 | 約510万円 |
40~44歳 | 約544万円 |
45~49歳 | 約590万円 |
50~54歳 | 約621万円 |
55~59歳 | 約626万円 |
60~64歳 | 約460万円 |
65~69歳 | 約370万円 |
70歳~ | 約388万円 |
最も平均年収が低かったのは19歳以下で、一番平均年収の高い年代は、55~59歳でした。
年代別の平均年収では、経験を積むとともに年収も高くなる傾向があるようです。
他業種と比較した平均年収
業種別に比較した平均年収は以下の通りです。
製造業 | 約591万円 |
建設業 | 約515万円 |
卸売業・小売業 | 約383万円 |
金融業・保険業 | 約631万円 |
運輸業・郵便業 | 約444万円 |
情報通信業 | 約622万円 |
医療・福祉 | 約397万円 |
サービス業 | 約397万円 |
ここでは金融業・小売業の平均年収が約631万円と2番高く、続いて情報通信業の約622万円となっています。
上位の業種に比べると製造業の591万円は劣るように見えますが、卸売業・小売業の約383万円やサービス業の約363万円と比較すると、平均年収は高くなっています。
建設業・運輸業・郵便業や医療・福祉関係の平均年収と比べても、製造業が特別劣っているわけではありません。
雇用形態別の賃金
雇用形態による賃金の違いは以下の通りです。
年齢 | 正社員 | 正社員以外 |
|---|---|---|
~19歳 | 約18.0万円 | 約17.4万円 |
20~24歳 | 約21.8万円 | 約18.3万円 |
25~29歳 | 約24.9万円 | 約20.2万円 |
30~34歳 | 約28.2万円 | 約20.7万円 |
35~39歳 | 約31.6万円 | 約21.4万円 |
40~44歳 | 約34.3万円 | 約21.2万円 |
45~49歳 | 約36.5万円 | 約21.2万円 |
50~54歳 | 約39.2万円 | 約20.9万円 |
55~59歳 | 約39.7万円 | 約21.2万円 |
60~64歳 | 約32.8万円 | 約24.1万円 |
65~69歳 | 約29.5万円 | 約21.6万円 |
70歳~ | 約28.3万円 | 約20.8万円 |
これは製造業に限った調査ではありませんが、年齢が若いうちは、それほど賃金に差はないようです。
19歳までの平均年収で、正社員と正社員以外の年収の差は1万円弱でした。
ただし勤続年数が増えるとともに、正社員とそれ以外の雇用形態では賃金の格差が大きくなっています。
一番差が大きくなったのは55~59歳で、約18万円の開きがありました。
参考:令和2年賃金構造基本統計調査の概況
学歴別の初任給
学歴による初任給の違いは以下の通りで
大学院修士課程修了 | 約23.8万円 |
大学卒 | 約20.6万円 |
高専・短大卒 | 約18.1万円 |
高校卒 | 約16.5万円 |
この調査も、製造業という括りで調査されたものではありませんが、初任給は学歴によって差があるようです。
一番低かったのが高卒の約16.5万円で一番高かった大学院修士課程修了者の約23.8万円と比較すると、7万円ほどの差があります。
参考:平成30年賃金構造基本統計調査結果(初任給)
製造業で年収を上げるには?

続いて、製造業で働くにあたり、年収を上げる方法を紹介します。
手当を考慮して働く
製造業は、他の業種に比べてさまざまな手当が充実している傾向があります。
- 役職手当
- 資格手当
- 残業手当
- 深夜手当
- 特殊作業手当
- 休日出勤手当 など
労働期間が決まっている期間工として働く場合は、入社祝いや満了祝いといった手当が付くこともあるでしょう。
シフト制で夜勤がある場合は、夜勤を多めにすることで、同じ時間働いても手当が付く分給料は高くなります。
資格を取得する
仕事に必要な資格を取ることで収入アップが見込めます。
資格手当が付く場合もありますし、資格があることで仕事の幅が広がるのでキャリアアップもしやすくなるでしょう。
ただし資格を取れば必ず資格手当が付くわけではありません。
勤務先に確認してからでなければ、「せっかく資格を取ったのに収入が変わらない」ということもあります。
具体的に優遇される資格は、後述する“製造業で優遇される資格“を参考にしてください。
転職する
職場の環境によっては、収入アップが見込めない場合もあるでしょう。
そのような状態であれば、転職するのも一つの方法です。
近年では減っているものの、いわゆる「3K」といわれる職場や、長時間労働やサービス残業を強いる職場は少なからずあります。
そういった会社でいくら頑張ったとしても、収入が上がる見込みはありません。
相場よりも明らかに年収が低い場合は転職も視野に入れましょう。
製造業で優遇される資格

製造業では、取得することで手当が付く資格があります。
携わる仕事によって必要な資格は変わりますが、ここでは優遇されやすい資格をチェックしましょう。
危険物取扱者
危険物取扱者は、ガソリンなどの危険物を取り扱うために必要な資格です。
資格区分は、甲種・乙種・丙種の3種類あります。
丙種の取得で第4類の危険物の一部、乙種の取得で試験に合格した危険物、甲種の取得で第1類から6類までのすべての危険物を扱えるようになります。
関連記事:危険物取扱者資格取得のメリットは?資格を活かした仕事内容
区分 | 受験資格 | 受験料 |
|---|---|---|
甲種 | 大学等において化学に関する学科等を修めて卒業した者 大学等において化学に関する授業科目を15単位以上修得した者 乙種危険物取扱者免状を有する者(実務経験2年以上 乙種危険物取扱者免状を有する者 修士・博士の学位を有する者 | 6600円 |
乙種 | 不問 | 4,600円 |
丙種 | 不問 | 3,700円 |
衛生管理者
安全で衛生的な職場環境を確保するのが衛生管理者の役割です。
常時50人以上の労働者が従事する職場に対し、事業規模に応じた人数を専任しなくてはなりません。
資格には、第一種衛生管理者と第二種衛生管理者があります。
第一種衛生管理者はどの業種でも衛生管理者として従事できますが、第二種衛生管理者は、商業やサービス業に関する業務に限定されます。
製造業で衛生管理者となるのであれば、第一種衛生管理者を取得しましょう。
関連記事:衛生管理者ってなに?試験の受験資格や資格取得のメリットについても解説
区分 | 受験資格 | 受験料 |
|---|---|---|
第一種衛生管理者 | 中卒:実務経験10年以上 高卒・公認試験合格者:実務経験3年以上 短大・専門学校・大学卒:実務経験1年以上 | 6,800円 |
第二種衛生管理者 | 第一種衛生管理者と同じ | 6,800円 |
電気工事士
電気工事士は、電気設備の設置やメンテナンスを行うために必要な資格です。
第二種電気工事士は��、一般的な住宅や店舗など、600V以下で受電する設備の工事ができます。
第一種電気工事士は、第二種の範囲に加え、最大電力500kW未満の工場やビルの工事ができるようになります。
関連記事:電気工事士はきついって本当?仕事内容や向いている人の特徴を紹介!
区分 | 受験資格 | 受験料 |
|---|---|---|
第一種電気工事士 | 不問 | 11,300円 |
第二種電気工事士 | 不問 | 9,600円 |
電子機器組立技能士
電子機器組立技能士は、電子機器を組み立てるために必要な技術と知識を有していることを証明する資格です。
資格には特級・1級・2級・3級があります。
区分 | 受験資格 | 受験料 |
|---|---|---|
特級 | 1級合格後、5年以上の実務経験 | 学科:3,100円 実技:18,200円 |
1級 | 2級合格後2年以上の実務経験 3級合格後4年以上の実務経験 7年以上の実務経験 | 学科:3,100円 実技:18,200円 |
2級 | 実務経験2年以上、もしくは3級の合格者 | 学科:3,100円 実技:18,200円 ※35歳未満の方は、実技9,200円 |
3級 | 不問 | 学科:3,100円 実技:18,200円 ※35歳未満の方は、実技9,200円 学科:3,100円 実技:18,200円 ※35歳未満の方は、実技9,200円 |
機械保全技能検定
機械保全技能検定は、工場の機械設備のメンテナンスを行うために必要な資格です。
特級・1級・2級・3級の資格区分があります。
試験は、機械系保全作業・電気系保全作業・設備診断作業の3種類あるので、仕事に必要な分野の試験を選択しましょう。
関連記事:機械保全技能士の検定の合格率は?資格取得のメリットや試験の内容も紹介!
区分 | 受験資格 | 受験料 |
|---|---|---|
特級 | 1級合格後5年以上の実務経験 | 学科・実技:20,000円 学科のみ:4,600円 実技のみ:15,400円 |
1級 | 7年以上の実務経験 2級合格後2年以上の実務経験 3級合格後4年以上の実務経験 | |
2級 | 2年以上の実務経験 3級の合格者 | |
3級 | 不問 |
製造業で働くメリット

製造業のメリットには、以下のようなものがあります
- 未経験でも働ける
- 通勤の服装や髪形が自由
- 労働時間が決まっている
各項目について具体的に見ていきましょう。
未経験でも働ける
製造業の求人は、「無資格・未経験可」としている求人がたくさんあります。
採用ハードルが比較的低めなので、製造業の経験がなくても働きやすいでしょう。
企業によっては、社員登用制度や、資格取得の支援制度を設けている場合もあります。
入社してから資格や技術を身に付けられるのも魅力です。
通勤の服装や髪形が自由
製造業では、勤務中は指定の作業着で働くことが多い傾向があります。
職場に着いてから作業着に着替えて働くので、通勤時の服装は比較的自由です。
髪の色やヘアスタイルも自由な職場が多いのですが、衛生面に厳しい職場の場合は、整髪料が使えない場合もあるでしょう。
労働時間が決まっている
製造業では、就業時間や休みが安定しています。
その日の作業内容やノルマが前もって決められており、仕事の進み具合を自分で把握可能です。
繁忙期は残業になることもありますが、それもある程度は予測ができるので、プライベートの予定も立てやすいでしょう。
寮や社食完備の企業も多く、福利厚生が充実していて働きやすいのもメリットの一つです。
関連記事:製造業のやりがいとは?向いている人・向いていない人を解説
製造業で働くデメリット

これから製造業に従事することを考えているのであれば、デメリットも把握しておきましょう。
製造業のデメリットには以下のようなものがあります。
- 勤務中は立ちっぱなし
- 単純作業が多い
勤務中は立ちっぱなし
製造業では立ち仕事が多く、勤務時間は基本的に立ちっぱなしです。
扱う製品によっては、重い荷物を持ち運ばなくてはならない職場もあります。
勤務先によっては、体力的な負担が大きくなるでしょう。
単純作業が多い
製造業の仕事には、ピッキング・仕分け・梱包・組み立て・加工など、さまざまな仕事があります。
どの仕事も難しくはありませんが、その半面単純作業の繰り返しになりがちです。
コツコツ作業を続けられる人ならよいのですが、人によっては「つまらない」「やりがいがない」と感じる人もいるでしょう。
まとめ

製造業の年収は低いといわれることもありますが、他業種と比べても、極端に低いということはありませんでした。
これから製造業に携わるのであれば、この記事で紹介した平均年収の目安を参考にしてください。
極端に賃金が低い求人は避けましょう。
収入アップを目指すのであれば、資格の取得や、賃金の高い夜勤で働くといった方法も検討してくださいね。








