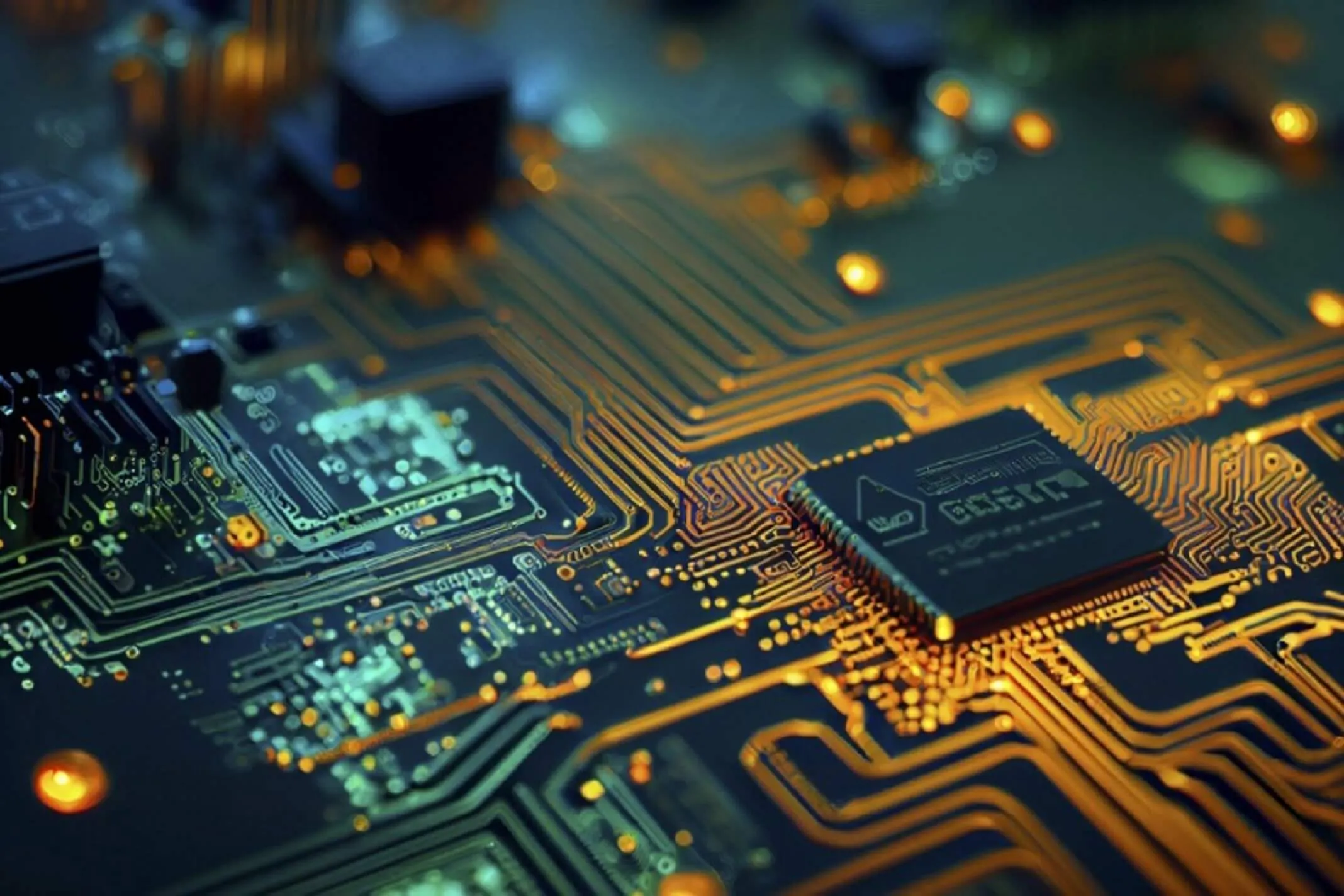MBTI(16パーソナリティ診断)で研究職に向いているタイプはどれ?強みも解説

近年、自分の性格特性を理解するツールとして注目を集めているMBTI(16パーソナリティ診断)。このMBTIを活用して、自分に適した職業を見つけたいと考える人が増えています。特に、研究職という専門性の高い分野を目指している方にとって、自分の性格タイプが研究活動に向いているかどうかは重要な判断材料の一つとなるでしょう。
研究職は、深い探究心と継続的な学習意欲、論理的思考力、そして時には長期間の孤独な作業に耐える集中力が求められる職業です。しかし、研究分野は多岐にわたり、基礎研究から応用研究、理論研究から実験研究まで、その性質は様々です。そのため、どのMBTIタイプが研究職に向いているかは、一概には言えない複雑な問題でもあります。
本記事では、MBTI の16タイプの中から研究職に特に適性があると考えられるタイプを詳しく解説し、それぞれの強みや研究分野での活かし方について具体的にお伝えします。
MBTI(16パーソナリティ診断)とは?

MBTI(エムビーティーアイ)とは、「Myers-Briggs Type Indicator」の略称で、ユングの心理学的タイプ論を元に、個人の性格を16タイプに分類する自己申告型の心理検査です。
MBTIは、個人を診断したり、性格の良し悪しを判断したりするものではありません。最大の目的は、自分自身の心を理解し、他人との違いを尊重することです。自己理解を深めることで、なぜ特定の行動や考え方をするのかを客観的に見つめ直し、円滑な人間関係やより良いキャリア形成に役立てることができます。
以下の4つの項目について、どちらに当てはまるかという「心の利き手」を判定し、その組み合わせで16タイプを決定します。
興味関心やエネルギーの方向 | E(外向型):人との交流や外界にエネルギーを得る I(内向型):内省や思考、一人で過ごす時間にエネルギーを得る |
|---|---|
情報収集の方法 | S(感覚型):五感で捉えられる、現実的で具体的な情報を重視する N(直観型):物事の全体像や可能性、未来のパターンを重視する |
意思決定の基準 | T(思考型):論理的で客観的な事実に基づいて判断する F(感情型):人や感情、価値観に基づいて判断する |
外界への接し方 | J(判断型):計画的で秩序を好む P(知覚型):臨機応変で柔軟性を好む |
これらの4つのアルファベットの組み合わせ(例:INTJ、ESFPなど)で、16の性格タイプが示されます。
【タイプ別】研究職の適性とキャリアのヒント

MBTIのタイプ別に見た、研究職の適性とキャリアのヒントをご紹介します。研究職は、論理的な思考力や探究心が求められるため、特にI (内向型)、N (直観型)、T (思考型)の要素を持つタイプが向いているとされます。
しかし、それぞれのタイプが持つ特性を活かせば、どのタイプでも研究職で活躍することは可能です。MBTIはあくまで自己理解を深めるためのツールであり、どのタイプも研究職として成功する可能性を秘めています。自分の強みを理解し、それを活かせる研究テーマや環境を見つけることが重要です。
論理的・分析的な研究者タイプ:INTJ,INTP,ENTJ,ENTP
これらのタイプは、論理的な思考力と客観的な分析力に優れており、研究職に最も向いていると言われています。
INTJ(建築家) | 完璧主義で、長期的な計画を立てて目標を達成する能力に長けています。複雑な研究テーマを体系的に解き明かすことに喜びを感じます。 |
|---|---|
INTP(論理学者) | 知的好奇心が旺盛で、物事の仕組みや原理を深く探求することに情熱を燃やします。既存の枠組みにとら�われない、革新的な研究に向いています。 |
ENTJ(指揮官) | リーダーシップがあり、研究プロジェクトを効率的に管理し、チームを牽引する能力に優れています。研究室のリーダーやプロジェクトマネージャーとして力を発揮するでしょう。 |
ENTP(討論者) | 新しいアイデアを次々と生み出すのが得意で、既存の概念を覆すような斬新な研究に挑戦します。 |
複雑な問題を論理的に分析し、仮説を立てて検証する業務が得意です。理論やモデルの構築、長期的な研究戦略の立案など、体系的なアプローチが求められる研究活動に適しています。
協調性・実践的な研究者タイプ:ISTJ,ESTJ,ISFJ,ESFJ
これらのタイプは、現実的な視点と高い協調性を活かして、着実に研究を進めることができます。
ISTJ(管理者) | 緻密な計画を立て、それを着実に実行する能力に長けています。実験データの整理や品質管理など、正確性が求められる分野で力を発揮します。 |
|---|---|
ESTJ(幹部) | 組織を効率的に動かすことが得意で、大規模な共同研究プロジェクトの進行管理に向いています。 |
ISFJ(擁護者) | 人の役に立ちたいという気持ちが強く、医療や社会科学と��いった、人々の生活に直接貢献する研究にやりがいを感じます。 |
ESFJ(領事) | チーム内の調和を重んじ、円滑な人間関係を築くのが得意です。共同研究において、潤滑油のような役割を果たすでしょう。 |
実用性の高い応用研究や、社会課題解決に直結する研究プロジェクトが得意です。チームでの共同研究、データ収集・整理、継続的な実験や調査など、地道で丁寧な作業が要求される研究活動に適しています。
また、研究結果を実際の製品やサービスに応用する橋渡し的な業務も得意とします。
直感的・創造的な研究者タイプ:INFJ, INFP, ENFJ, ENFP
これらのタイプは、豊かな想像力と共感力を活かして、独創的な研究をすることができます。
INFJ(提唱者) | 強い信念を持ち、社会貢献につながるような研究に深く取り組むことができます。 |
|---|---|
INFP(仲介者) | 自分の価値観を大切にし、興味を持った分野を深く掘り下げます。人文学や芸術といった、創造性が求められる分野で力を発揮します。 |
ENFJ(主人公) | 人々を鼓舞し、研究チームのモチベーションを高めるのが得意です。教育者や研究チームのメンターとして活躍するでしょう。 |
ENFP(広報運動家) | 新しい可能性を探求するのが好きで、複数の研究テーマに興味を持ちます。異分野間の連携研究などに向いています。 |
人文社会科学分野の研究や、人間の心理・行動に関する研究が得意です。質的調査、フィールドワーク、創造性を要求される研究手法の開発など、従来の枠組みを超えた新しいアプローチが求められる研究活動に適しています。
また、研究成果を一般の人々に分かりやすく伝える啓発活動や教育的な業務も得意とします。
柔軟・好奇心旺盛な研究者タイプ:ISTP, ESTP, ISFP, ESFP
これらのタイプは、実践的なスキルと即興性を活かして、研究を進めることができます。
ISTP(巨匠) | 手先が器用で、実験装置の組み立てやプログラミングなど、実践的な作業を好みます。試行錯誤を繰り返しながら、研究課題を解決していくことにやりがいを感じます。 |
|---|---|
ESTP(起業家) | 行動力があり、フィールドワークなど、実際に現場に出てデータを集める研究に向いています。 |
ISFP(冒険家) | 自分の感覚を大切にし、新しい表現方法や独自の視点から研究を行います。 |
ESFP(エンターテイナー) | 人と関わるのが好きで、研究成果を分かりやすく発表したり、学会で交流したりする活動に力を発揮します。 |
実験や実習を中心とした実践的な研究、フィールドワークや現場調査が得意です。新しい実験手法の試行錯誤、機器の操作や改良、予期せぬ現象への対応など、柔軟性と実用的なスキルが求められる研究活動に適しています。
また、研究成果をデモンストレーションやワークショップ形式で発表する活動も得意とします。
MBTIを研究職で活かすための具体的なステップ
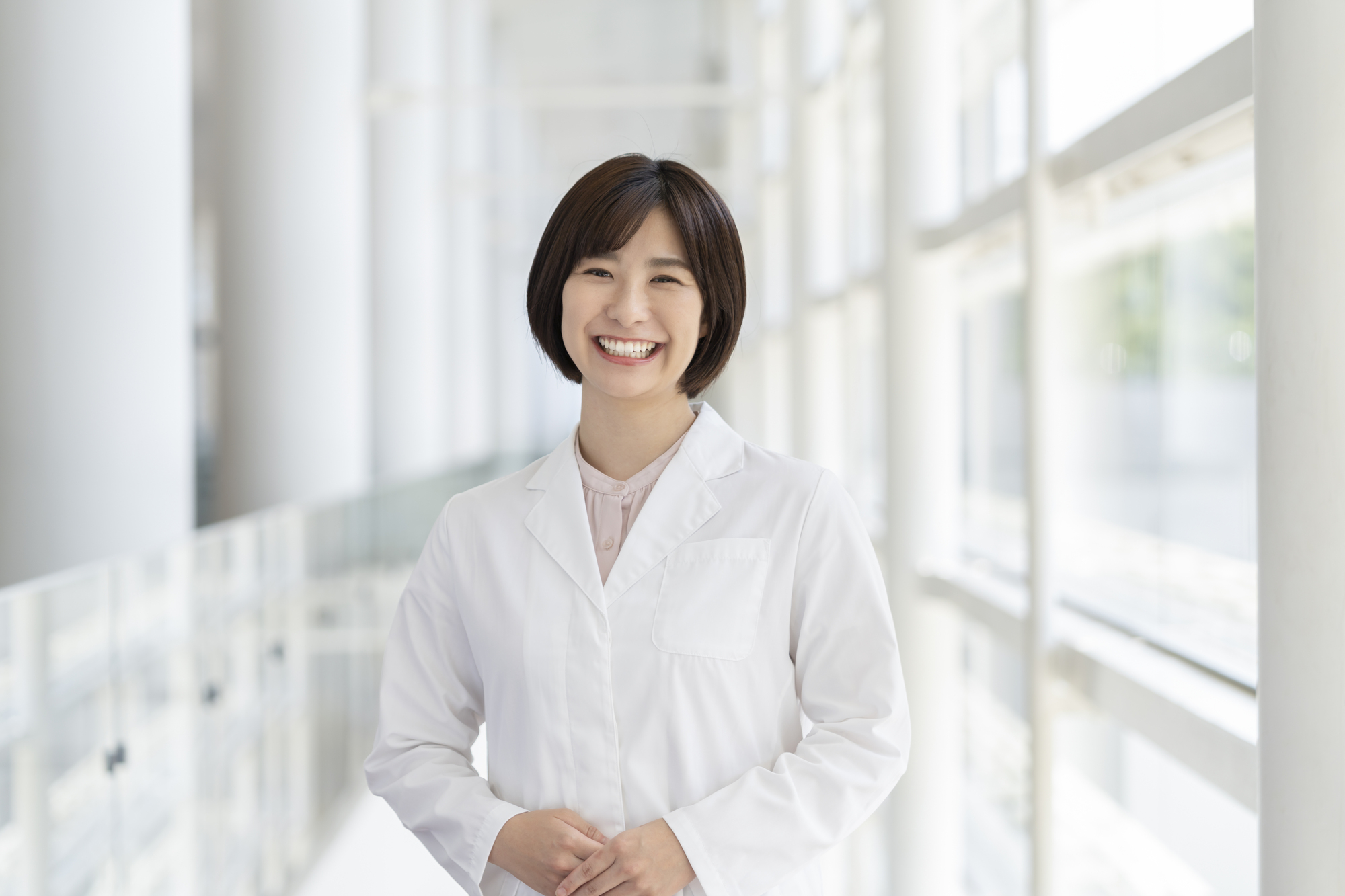
MBTIを研究職で活かすための具体的なステップは、まず自己理解を深め、自分の強みを把握することです。次に、その強みを活かせる研究テーマや役割を見つけ、キャリアプランに繋げていくことが重要です。
1.自分のタイプを知る
まずは信頼できるサイトでMBTI診断を受けて、自分のタイプを確認しましょう。診断を受ける際は、理想の自分ではなく現在の自分に正直に答えることが重要です。一度の診断結果だけでなく、複数の診断を試したり、時期を変えて再度受診したりして、より正確な自己理解を深めることをお勧めします。
また、診断結果について詳しく調べ、各機能(外向性/内向性、感覚/直感、思考/感情、判断/知覚)がどのような特徴を持つのか理解を深めましょう。自分の行動パターンや価値観と照らし合わせながら、結果に納得感があるか検証することも大切です。
2.強みを活かす研究テーマを探す
自分のタイプの特徴と照らし合わせ、どんな研究テーマや働き方が自分に合っているか考えてみましょう。たとえば、論理的思考が得意なタイプなら理論研究や数理モデルの構築、協調性に優れるタイプなら学際的な共同研究、創造性豊かなタイプなら新しい研究手法の開発などが適している可能性があります。
また、研究環境についても検討しましょう。一人で集中したいタイプは個人研究室、チームワークを重視するタイプは共同研究室、柔軟性を求めるタイプはフィールドワーク中心の研究など、自分の性格に合った環境を選ぶことで研究効率が向上します。興味のある分野と自分の強みが重なる領域を見つけることが、長期的に充実したキャリアを築く鍵となります。
3.弱みを理解し、補う方法を考える
すべてのMBTIタイプには得意分野と苦手分野があります。例えば、内向的なタイプなら外部との連携や大人数でのプレゼンテーションが苦手な可能性があります。その場合は、事前に準備をしてからミーティングに臨む、得意な人に協力を依頼する、少人数での議論から始めるなど、具体的な対策を立てることができます。
思考型のタイプなら感情的なコミュニケーションが苦手かもしれませんし、感情型のタイプなら客観的な批判を受け入れることが困難な場合もあります。このような弱みを認識した上で、苦手分野をカバーするスキルを身につけたり、補完してくれるパートナーを見つけたりすることで、研究活動をより円滑に進めることができます。
4.多様なタイプの人と協働する
研究はチームで行うことがほとんどであり、自分とは違うタイプの人と協力することで、新たな視点が生まれ、より質の高い研究につながります。論理的思考が得意な人と創造的発想が豊かな人が組むことで、厳密性と革新性を兼ね備えた研究が可能になります。
また、内向的なタイプと外向的なタイプが協力すれば、深い思考と幅広いネットワーキングの両方を活かした研究展開が期待できます。チーム内で各メンバーの強みを理解し、適切な役割分担を行うことで、個人では達成できない高いレベルの研究成果を生み出すことができるでしょう。異なるタイプの人との協働は、自分自身の成長機会にもなります。
まとめ
MBTIは研究職への適性を測る一つの指標として活用できますが、どのタイプにもそれぞれの強みがあり、研究分野で活躍する可能性を秘めています。重要なのは自分のタイプを理解し、強みを活かせる研究テーマや環境を見つけること、そして弱みを補完しながら多様なチームメンバーと協働することです。MBTIを自己理解のツールとして活用し、自分らしい研究キャリアを築いていきましょう。
研究開発分野でのキャリアにご興味をお持ちの方は、ワールドインテックのRD事業部にご相談ください。多様な性格タイプの研究者が活躍できる環境を整備し、個々の強みを活かしたプロジェクト配置を行っています。あなたの可能性を最大限に発揮できる研究の場を一緒に見つけましょう。