エネルギー管理士は意味ないって本当?その理由や取得するメリットを詳しく解説!

エネルギー管理士とは、エネルギー使用に関する国家資格で、工場などでエネルギー使用方法の改善、管理をするのが主な仕事です。資格は受験に条件がない国家試験か、実務経験が一定年数必要な研修の修了試験に合格することで取得できます。合格率は、国家試験で約30%、研修試験で約60%です。本記事でエネルギー管理士のメリット、資格の試験内容や必要な勉強時間などを把握し、エネルギー管理士の理解を深めましょう。
エネルギー管理士とは?
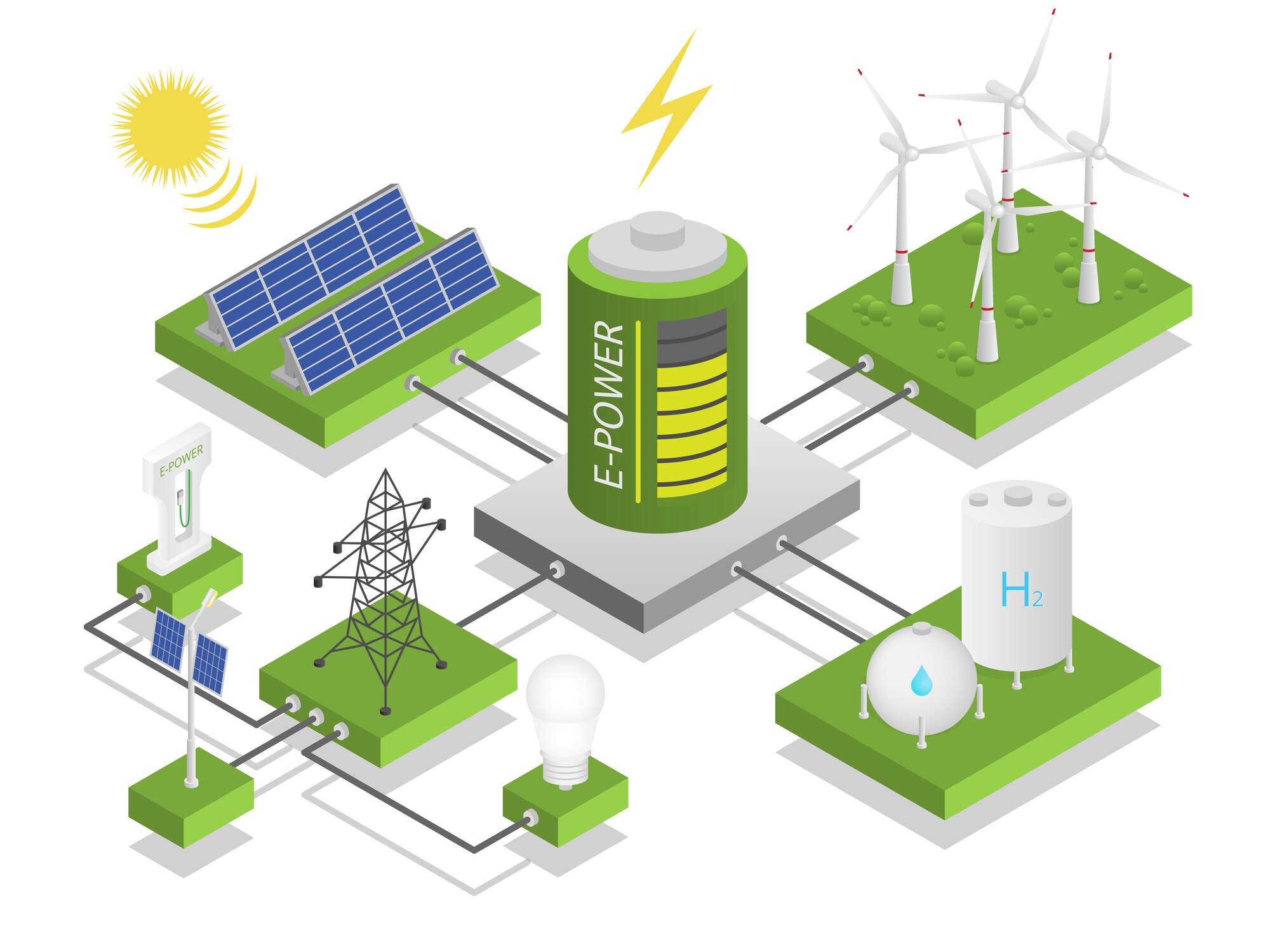
エネルギー管理士とは、限りある資源を効率的に活用するため定められた国家資格で、エネルギーの使用方法を改善・管理するのが仕事です。下記で、エネルギー管理士と本資格ができた背景について解説します。
省エネ法により定められた国家資格
エネルギー管理士とは、2006年に省エネ法により定められた国家資格で、工場内のエネルギー使用方法の改善、管理をします。規定量以上のエネルギーを使う工場には、本資格を所持する者がいなければなりません。以前は熱管理士、電気管理士と別個の資格でしたが、2006年の省エネ法改定によりエネルギー管理士としてまとめられました。
エネルギー管理士ができた背景
エネルギー管理士という資格が誕生した理由は、エネルギー自給率の低い日本において、有限な資源を無駄なく活用するためです。国全体で省エネの動きを取っており、工場のように多量にエネルギー消費をする場では、省エネは大きな課題です。エネルギー管理士は工場内のエネルギーの使用量などを管理し、使用量削減を目指すため、工場に欠かせない存在です。
エネルギー管理士が必要な工場
エネルギー管理士の必要有無については、省エネ法に基づき、下記のように定められています。
- 必要な工場は、規定量以上のエネルギーを使用する工場のうち、製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の5業種
- エネルギーの使用量に応じ、エネルギー管理士を1人ないしネルギー管理者を4人選任する義務がある
規模の大きい工場であればあるほど、エネルギー管理士は必須になってきます。
エネルギー管理士の仕事内容

エネルギー管理士の仕事内容は?
エネルギー管理士の主な仕事は、工場内のエネルギー使用量の管理です。基本的には、省エネを目指しエネルギー使用量の削減対策を実施します。工場内で過剰に電気や熱エネルギーを使用している箇所を見つけ、削減対策案を経営者に提示します。意見を伝える際には、経営者が納得できるよう、削減効果の程度やメリットなどを具体的に伝えることが重要です。
エネルギー管理者とエネルギー管理員になれる
エネルギー管理士の資格を保有していれば、エネルギー管理者とエネルギー管理員になれます。エネルギー管理者やエネルギー管理員は、工場の規模に合わせて選任が義務付けられている職種です。工場としても、エネルギー削減はコストカットにつながるため、積極的に取り入れたい分野であり、専門家の知識が求められるシーンは多いでしょう。
エネルギー管理士資格試験とは
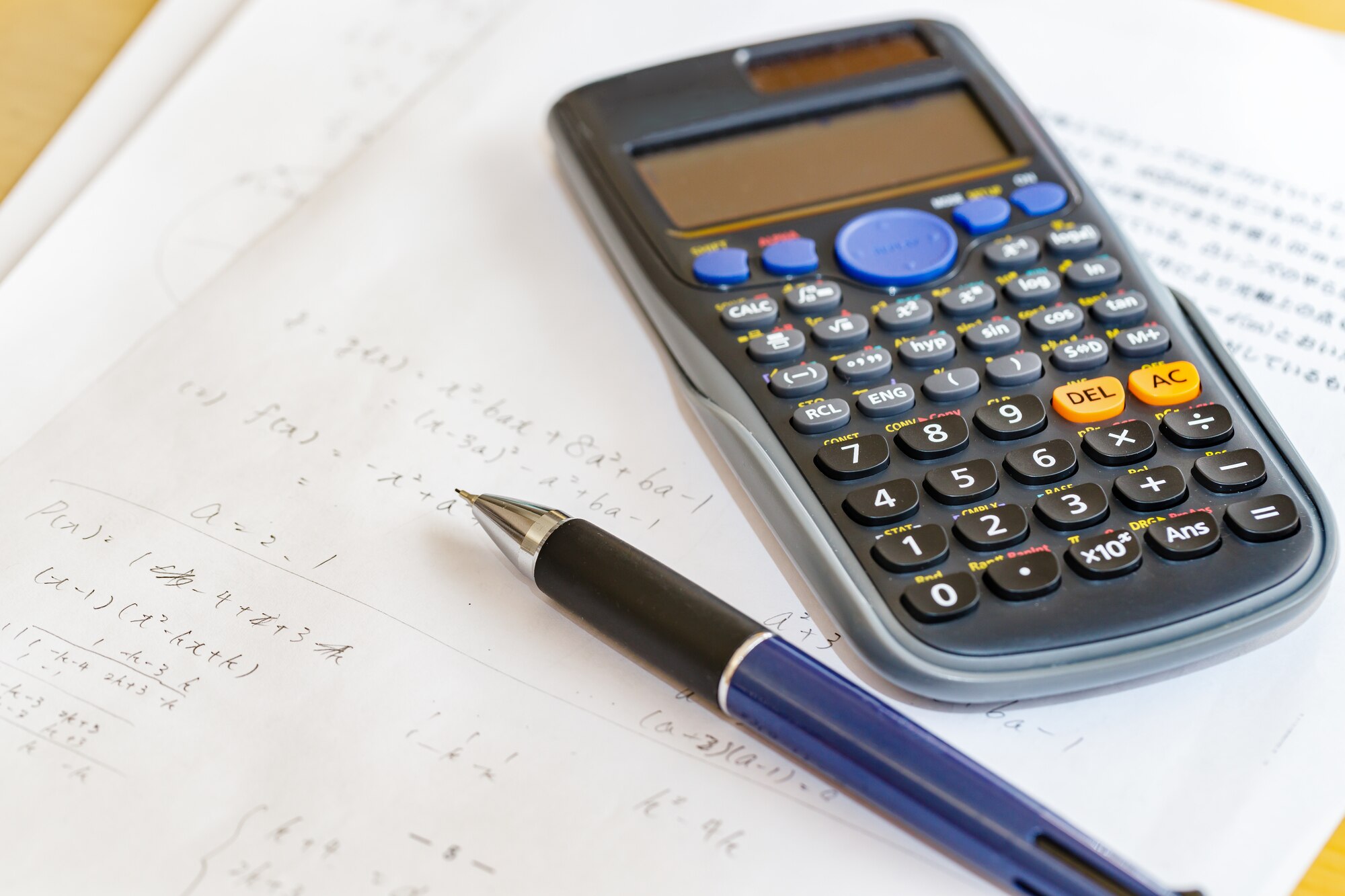
エネルギー管理士資格の取得方法は試験と研修の二つ
エネルギー管理士の資格を取得する方法は、二つあります。一つは、国家試験を受け合格する方法、もう一つは、認定研修を受け、修了試験に合格する方法です。下記は、国家試験を受ける際の基準などです。
受験条件 | なし。誰でも受験できる |
|---|---|
試験方法 | マークシート式 |
試験日 | 毎年8月 (2022年は7月31日、2021年は8月8日に実施) |
受験料 | 17,000円 ※旧制度資格保有者など、一定条件を満たす場合10,000円 |
試験会場 | 北海道、宮城県、東京都、愛知県、富山県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県 |
試験内容と合格基準 | 必須基礎区分および熱分野専門区分または、必須基礎区分および電気分野専門区分のいずれか一つの分野を選択。各課目の合格基準である配点の60%以上の得点で合格 |
合格率 | 令和4年度:33.9% 令和3年度:31.9% |
認定研修に関する概要は、下記の通りです。
研修応募条件
研修応募条件 | 申込時までに、エネルギー使用合理化に関する実務に3年以上従事 |
|---|---|
試験方法 | 記述式 |
研修日程 | 12月上旬~中旬(研修地・分野により異なる) |
研修受講料 | 70,000円 ※前年度研修にて修了試験の一部に合格している者など条件を満たす場合50,000円 |
研修会場 | 宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
研修内容 | 熱分野、電気分野の講義を合計6日間、修了試験1日 |
合格率 | 60%前後 |
資格試験の場合は、応募に条件がないため誰でも受けられます。ただし、合格率は30%前後であり、難易度は高めです。一方、研修は3年以上エネルギー合理化に関する実務経験を積んでいる必要があります。その分、修了試験の合格率は約60%と、国家試験よりも高い数値が出ています。
試験科目は熱分野と電気分野を選択できる
試験では、共通科目である必須基礎区分のほかに、熱分野と電気分野のどちらかを選択できます。どちらを選択しても、合格すればエネルギー管理士として熱分野・電気分野両者の管理者になれます。試験では、得意なほうや、将来取得する可能性がある資格の分野に近いものを選びましょう。例えば、ボイラー技士や、冷凍機械責任者、危険物取扱者などは熱分野に関係し、電気主任技術者試験には電気分野が関わります。下記で各分野について簡単に説明します。
熱分野
熱分野の試験では、熱利用設備に関する知識や管理方法、熱力学、燃料と燃焼などについて問われます。熱力学では、熱・気体の流れなどを学びますが、工学部系の大学で学ぶ専門性の高い知識です。しかし、似たような問題が出やすい傾向にあるので、初めて学ぶ人でも過去問対策をすれば、取り組みやすい分野でといえるでしょう
電気分野
電気分野では、電気基礎の電気および電子理論、電気化学や電気加熱、電気設備に関する問題が出ます。高校物理の範囲内の知識から、専門的な部分まで幅広く問われます。計算問題が多いため、過去問で対策する必要があります。
エネルギー管理士資格の難易度は

エネルギー管理士の国家試験の合格率と、研修試験の合格率を見てみましょう。
国家試験 | 研修試験 | |
令和4年度(2022年) | 33.9% | ― |
令和3年度(2021年) | 31.9% | 61.2% |
令和2年度(2020年) | 36.7% | 65.2% |
令和元年(2019年) | 32.6% | 54.8% |
国家試験の合格率は約30%と低く、試験の難易度は高めです。一方、研修試験の合格率は60%前後と高い傾向にあります。試験勉強に必要な時間は予備知識の程度によりますが、最低でも100時間程度は必要でしょう。仕事をしながら1日30分~1時間勉強したとしても、最低で3カ月~半年はかかります。専門的な知識を問われるため、初めて学ぶ場合、1年以上勉強に費やす気持ちで取り組むとよいでしょう。
エネルギー管理士試験の勉強方法
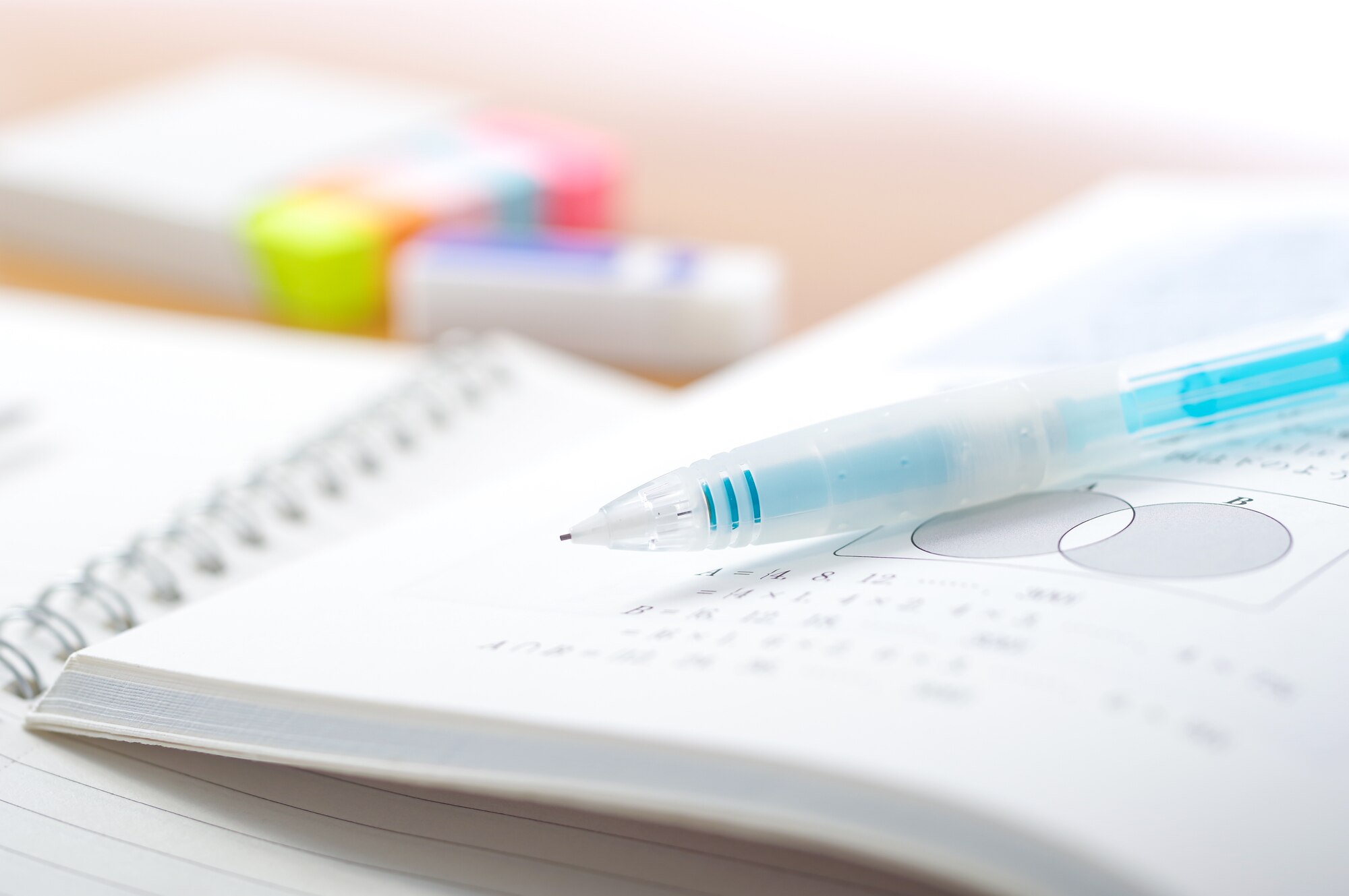
エネルギー管理士試験の試験勉強方法は、下記の通りです。
- 過去問を繰り返し解く
- 隙間時間を利用し、暗記する
- 通信講座などを活用し、理解を深める
資格試験の勉強方法で重要なのが、過去問を解くことです。過去問で出題傾向を把握し、自分の得手不得手分野を発見すれば、勉強の効率が上がります。また、試験までは休み時間や通勤時間など、隙間時間を有効活用するように努めましょう。単語の暗記であれば王道の単語カードや、赤シートを使ったり、暗記用のアプリなどを活用したりする方法もあります。また、なかなか勉強時間を確保しにくいときや、過去問・参考書の解説では不十分な場合、通信講座を活用するのも一つの方法です。通信講座では専用のテキストを使うため、独学よりも理解しやすいはずです。受験料が高い分、少ない回数で合格するために、活用できるものに投資し、合格をつかみ取りましょう。
エネルギー管理士資格は本当に意味がないのか?その理由3つ
一見すると専門性も高くて価値がありそうに見えます、実際には「意味ない」「役に立たない」と言われることも少なくありません。その理由をご紹介します。
実務で資格の知識が活かせないことがある
試験に出る内容は非常に幅広く、法令や技術の全般的な知識が求められます。ただ、日々の現場の仕事では、そのすべてを使い切れないこともあります。担当業務や配属先によっては、せっかくの資格を活かせないと感じる方も。「勉強したのに仕事に直結しない」とモヤモヤしてしまうこともあるでしょう。
資格だけではキャリアアップに直結しにくい
「資格を取ればスッと昇進!」というわけではありません。実務経験や人間関係、タイミングなど、昇進には他の要素も絡みます。エネルギー管理士はあくまで基礎的なスキル保証の一つ。資格保持だけでは、その後のキャリアが自動的に開けるわけではないため、「意味ない」と捉えられることがあります。
取得にかかるコスト(時間・労力)が大きい
合格までに必要な勉強時間は300〜600時間とも言われ、その準備期間は半年から1年以上かかります。仕事や家庭と両立しながら、長期間にわたる勉強をこなすのは簡単ではありません。この負担感に対して効果が見合わないとして、意味がないという考える方もいるのです。
しかし、資格はあくまで「土台」。これを活かして実務経験を積み重ね、スキルに磨きをかけることこそが本当の意味でのキャリアアップにつながります。
エネルギー管理士資格を取得するメリット

難易度が高めのエネルギー管理士ですが、取得すれば工場に欠かせない人材となり、今後活躍の場が増えていくでしょう。また、難易度の高い国家資格は所有者が少ないため、転職の際にも有利です。下記で、エネルギー管理士の資格を取得するメリットを解説します。
今後活躍の場が広がる傾向にある
国全体で省エネが推進されているため、今後需要が伸びる可能性があります。再生可能エネルギーの導入や、エネルギー使用の効率化、経費削減を目指している工場で活躍が見込めるでしょう。
なくてはならない人材になれる
規定量以上のエネルギーを使用する工場には、エネルギー管理士の選任が義務付けられています。また、エネルギー運用に関し、削減対策を経営者に伝える必要があるため、工場の運営に関わることになります。エネルギー管理士は、工場にとって欠かせない人材となるでしょう。
転職の際も優遇されやすい
エネルギー管理士は、難易度の高い国家資格のため、取得していれば転職に有利に働くでしょう。大型の商業施設やオフィスビルなど、エネルギーを大量消費する物件で需要があり、工場以外の転職先も視野に入れられます。
まとめ

エネルギー管理士とは、エネルギー使用に関する国家資格で、工場などの施設におけるエネルギー使用量を管理し、使用量削減方法を提案します。規定量以上のエネルギーを使用する工場では設置が義務付けられているため、工場にとって必要不可欠な人材といえます。エネルギー管理士になるには、国家試験を受けるか、研修を受けなければなりません。今後需要の増加が見込める資格であり、工場以外でも商業施設やオフィスビルなど、エネルギーを多量に消費する場所で活躍できるでしょう。








