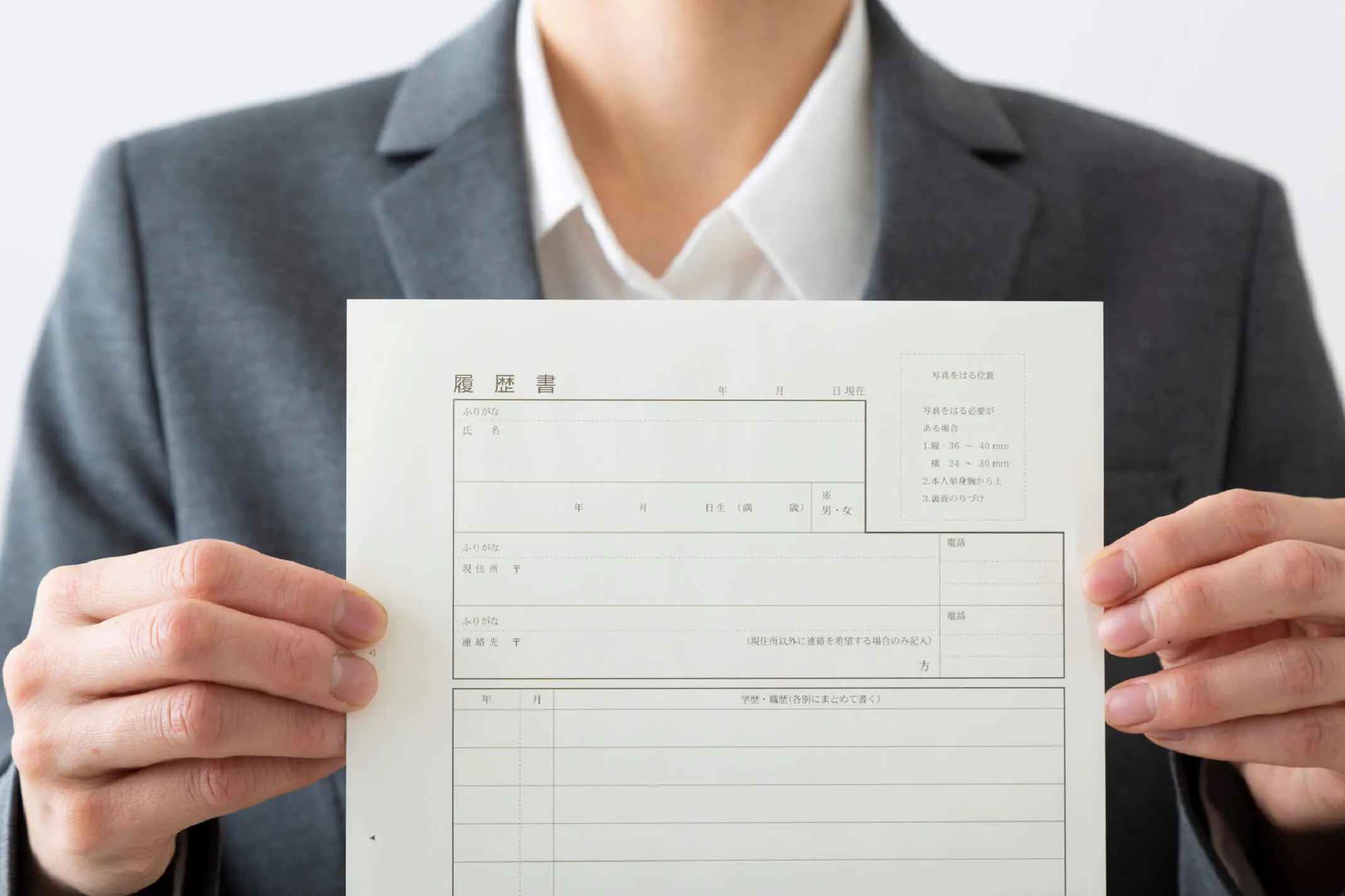研究職でつらいことあるある5選!向いていない人の特徴、やりがいについても解説

研究職は「未知の領域を探究し、新たな発見や知識創造に貢献できる」という魅力的な側面がある一方で、実際に働いてみると想像以上の困難に直面することも少なくありません。長期間にわたる地道な実験や調査、思うような結果が得られない日々、限られた予算や時間の中でのプレッシャーなど、研究職特有の悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
また、研究職への憧れから転職を考えているものの、「自分に本当に向いているのか」�「どんな苦労があるのか」と不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。研究職は一般的な職種とは異なる特殊な環境であるため、事前に現実を知っておくことが重要です。
この記事では、研究職で働く人が実際に体験している「つらいこと」を5つのポイントに整理し、研究職に向いていない人の特徴や、それでも多くの研究者が感じているやりがいについて詳しく解説します。研究職への理解を深めることで、キャリア選択の参考にしていただければと思います。
研究職とは

研究職とは、主に民間企業、大学、公的機関などの研究所で、特定の専門分野について研究を行う職種を指します。新しい知識や技術、理論を発見したり、それらを実用化する方法を考えたりするのが主な仕事です。
主な仕事内容
研究職の仕事は、まず特定の分野における最新の研究動向や先行研究を調査し、解決すべき課題や仮説を明確に設定することから始まります。課題が定まったら、限られた予算と時間の中で効率的に研究を進めるための詳細な計画を立案し、必要な実験設備や材料の準備を行います。
実際の研究活動では、計画に基づいて実験や調査を繰り返し実施し、得られたデータを統計的手法や専門的な分析ツールを用いて解析します。結果の考察では、仮説との整合性を検証し、新たな発見や知見を導き出します。
これらの成果は学術論文として執筆し、学会での発表や査読付きジャーナルへの投稿を通じて研究コミュニティに共有します。また、実用的な価値のある発見については特許申請を行い、社会実装への道筋をつけることも重要な業務の一つです。
研究職の仕事に就いては以下の記事でも紹介しているので、あわせてご覧ください。
【関連記事】研究職はどんな仕事?就職先や働く魅力・就職を有利に進めるポイントも解説
研究職の種類
研究職は大きく分けてアカデミア(学術機関)と企業の2つの領域に分類されます。
アカデミアには大学や国立研究機関、公的研究所などが含まれ、基礎研究を中心とした知識の創造と教育が主な使命となります。ここでは研究者自身の興味や学術的価値に基づいてテーマを選択でき、長期的な視点で研究に取り組むことが可能です。一方で、競争的資金の獲得や論文発表による業績評価が重要となり、不安定な雇用形態も課題となっています。
企業研究職では、製品開発や技術革新につながる応用研究が中心となり、市場ニーズや企業戦略に沿った研究テーマが設定されます。比較的安定した雇用と給与が期待できる反面、研究期間や予算の制約が厳しく、短期的な成果が求められる傾向があります。
また、研究成果の公表に制限があることも特徴です。どちらの道を選ぶかは、研究への取り組み方や価値観、キャリアビジョンによって決まります。
なお、研究者の種類については以下の記事でも解説しています。
【関連記事】研究者の種類は豊富!仕事内容やよくある就職先・おすすめの資格も解説
研究職が「きつい」「やめとけ」と言われるのはなぜ?つらいことあるある5選

研究職が「きつい」「やめとけ」と言われるのには、いくつかの理由があります。特に、以下のような点が挙げられ、それが「つらい」と感じられる要因となることが多いです。
終わりが見えない地道な作業
研究の多くは仮説検証のための反復実験や膨大なデータ収集作業で構成されており、一つの実験結果を得るために何ヶ月も同じ作業を続けることは珍しくありません。
特に基礎研究では、明確な終了点が設定されていないため、いつまで続ければよいかわからない状況に陥りがちです。実験の失敗や予期しない結果により、当初の計画が大幅に変更されることもあり、精神的な疲労が蓄積していきます。
成果が出ないプレッシャー
研究は本質的に不確実性を伴う活動であり、長期間努力しても期待した成果が得られないことが頻繁にあります。しかし、学術機関では論文発表数や被引用数による評価、企業では開発目標の達成が求められるため、結果が出ない期間が続くと強いプレッシャーを感じます。
特に若手研究者にとって、キャリア形成に直結する成果を出せない焦りは深刻な悩みとなります。
研究費獲得の壁
研究活動には実験設備、材料費、人件費など多額の資金が必要ですが、競争的研究費の採択率は非常に低く、優秀な研究者でも資金獲得に苦労するのが現実です。
申請書類の作成には膨大な時間を要し、不採択になれば研究計画の見直しを余儀なくされます。安定した研究環境を維持するため、常に複数の資金源確保に奔走する必要があり、本来の研究時間が削られてしまいます。
人間関係と孤独
研究室やプロジェクトチーム内での人間関係は研究環境に大きく影響しますが、指導教員や上司との相性、同僚との競争関係などでストレスを抱えることがあります。
一方で、高度に専門化された研究内容は一般の人には理解されにくく、研究の悩みや喜びを共有できる相手が限られるため、孤独感を感じる研究者も少なくありません。特に博士課程の学生や若手研究者は、将来への不安も相まって孤立感を深めがちです。
ワークライフバランスの難しさ
研究は創造的な活動であるため、アイデアが浮かんだときや実験が順調に進んでいるときには時間を忘れて没頭してしまいがちです。
また、実験のタイミングや学会発表の締切などにより、不規則な勤務時間になることも多く、プライベートの時間確保が困難になります。特にアカデミアでは成果主義的な側面が強く、長時間労働が常態化しやすい環境にあるため、家族との時間や趣味の時間を犠牲にしてしまう研究者も多いのが現状です。
研究職が「やめとけ」と言われる理由については、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:研究職はやめとけと言われる理由とは?研究職がおすすめの理由6つ
研究職に向いていない人の特徴

研究職は、知的好奇心旺盛で探求心の強い人にとっては非常にやりがいのある仕事ですが、一方で、特定の特徴を持つ人にはストレスや困難が多いと感じられることがあります。以下に、研究職に向いていない可能性のある人の特徴をまとめました。
これらの特徴に当てはまるからといって、必ずしも研究職になれないわけではありませんが、研究職として働く上で大きな障壁となる可能性があることを理解しておくことが大切です。
短期間で結果を求める人
研究は本質的に長期的な取り組みが必要な活動であり、一つの研究テーマでも数年から十数年かけて成果を積み上げていくのが一般的です。すぐに目に見える成果や達成感を求める人にとって、研究の進歩は非常にゆっくりと感じられるでしょう。
実験の失敗や予期しない結果に直面した際に、すぐに方向転換を求めたり諦めてしまったりする傾向がある人は、研究職には不向きです。研究には忍耐力と持続力が不可欠であり、小さな進歩を積み重ねることに価値を見出せる姿勢が求められます。
論理的思考が苦手な人
研究活動は仮説の設定から実験設計、データ解析、結論導出まで、すべてのプロセスで論理的な思考が要求されます。感情や直感だけで判断する傾向が強い人や、因果関係を整理することが苦手な人は、研究の質を保つことが困難になります。
また、研究結果を他者に説明する際や論文執筆時にも、論理的で説得力のある構成が必要となるため、この能力が不足していると研究者としての評価を得ることが難しくなります。
細かい作業が苦手な人・大雑把な人
研究では実験条件の微細な調整、データの正確な記録、実験手順の厳密な管理など、非常に細かい作業が日常的に発生します。小さなミスが研究結果全体に影響を与える可能性があるため、注意深さと正確性が重要な資質となります。
大雑把な性格で詳細への注意を払うことが苦手な人は、実験の再現性を確保できなかったり、重要なデータを見落としたりするリスクが高く、信頼性の高い研究を行うことが困難になります。
コミュニケーションを避ける人
研究は一人で完結する作業ではなく、指導教員や同僚との議論、共同研究者との連携、学会での発表、査読者との対話など、様々な場面でコミュニケーションが必要です。自分の考えを他者に伝えることを避けたり、他者からのフィードバックを受け入れたりすることが苦手な人は、研究の質向上や新たな視点の獲得が困難になります。
また、研究成果の社会への還元においても、効果的なコミュニケーションは不可欠な要素となります。
知的好奇心が薄い人
研究の原動力となるのは「なぜだろう」「どうすればできるだろう」という知的好奇心です。この好奇心が薄い人は、困難な問題に直面した際に諦めやすく、新しい知識や技術を学び続けるモチベーションも維持できません。研究分野は常に進歩しているため、継続的な学習と探究心がなければ、時代遅れの研究者となってしまいます。
また、研究テーマに対する深い関心がなければ、長期間にわたる地道な作業を続けることも困難になります。
【関連記事】研究職に向いている人の特徴5選!仕事内容やメリット・デメリットについても解説
研究職として働くやりがい

研究職は「きつい」「やめとけ」と言われることもありますが、それ以上に大きなやりがいを感じられる仕事です。特に、以下のような点が研究者にとっての大きなモチベーションとなります。
新しい発見・創造の喜びがある
研究職の最大の魅力は、これまで誰も知らなかった事実を発見したり、新しい技術や理論を生み出したりする瞬間の感動です。長期間にわたる実験や調査の末に、予想外の結果が得られたときや、仮説が実証されたときの喜びは、他の職業では味わえない特別な体験となるでしょう。
自分の手で未知の領域を切り開き、人類の知識体系に新たな一ページを加えることができるという達成感は、研究者にとって何物にも代えがたい価値があります。
また、創造的な問題解決プロセスを通じて、自分自身の能力や可能性を発見することも大きなやりがいの一つです。
社会貢献への実感を味わえる
研究成果が実際に社会問題の解決や人々の生活向上に役立つ場面を目にすることで、深い充実感を得ることができます。医療分野では新薬の開発や治療法の改善、環境分野では持続可能な技術の開発、情報技術分野では生活を便利にするシステムの構築など、研究が直接的に社会に貢献する機会は多いです。
自分の研究が誰かの役に立っている、世の中をより良くしているという実感は、研究活動の困難さを乗り越える大きな原動力となるでしょう。また、次世代の研究者や学生を指導することで、知識の継承と人材育成にも貢献できます。
自分の趣味や好きなことを活かせる
研究職では、自分の興味関心や得意分野を仕事に直結させることができるため、「好きなことを仕事にする」理想的な働き方を実現できます。幼少期からの疑問や趣味が研究テーマに発展することもあり、プライベートの時間と仕事の境界が曖昧になるほど没頭できる環境があります。
また、研究分野の多様性により、文系理系を問わず様々な興味を持つ人が活躍の場を見つけることができます。自分の価値観や哲学を研究活動に反映させながら、生涯をかけて追求したいテーマに取り組むことで、単なる職業を超えた人生の使命感を感じることができるのも研究職の大きな魅力です。
【関連記事】研究職の年収は1000万超えできる?実態や到達するためのポイントを解説
まとめ
研究職は確かに多くの困難や挑戦を伴う職業ですが、新しい発見や創造の喜び、社会貢献への実感、自分の興味を活かせる環境など、他では得られない大きなやりがいがあります。重要なのは、研究職の現実を正しく理解した上で、自分の性格や価値観と照らし合わせて判断することです。
もし長期的な視点で物事に取り組むことができ、知的好奇心が旺盛で、困難にも粘り強く向き合える方であれば、研究職は非常に充実したキャリアパスとなるでしょう。研究という仕事を通じて、自分自身の成長と社会への貢献を同時に実現できる素晴らしい職業といえます。
研究職に関心を持った方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。
【関連記事】研究職は未経験でも働ける?実態やキャリアを積む方法について解説
ワールドインテックのRD事業では、経験や適応に応じた職種への就業、エリア希望や家庭の都合における勤務地・通勤の考慮など働きやすい環境を提供しています。
研究職でより高みを目指したいと考えている方は、ぜひワールドインテックに応募してみてください。