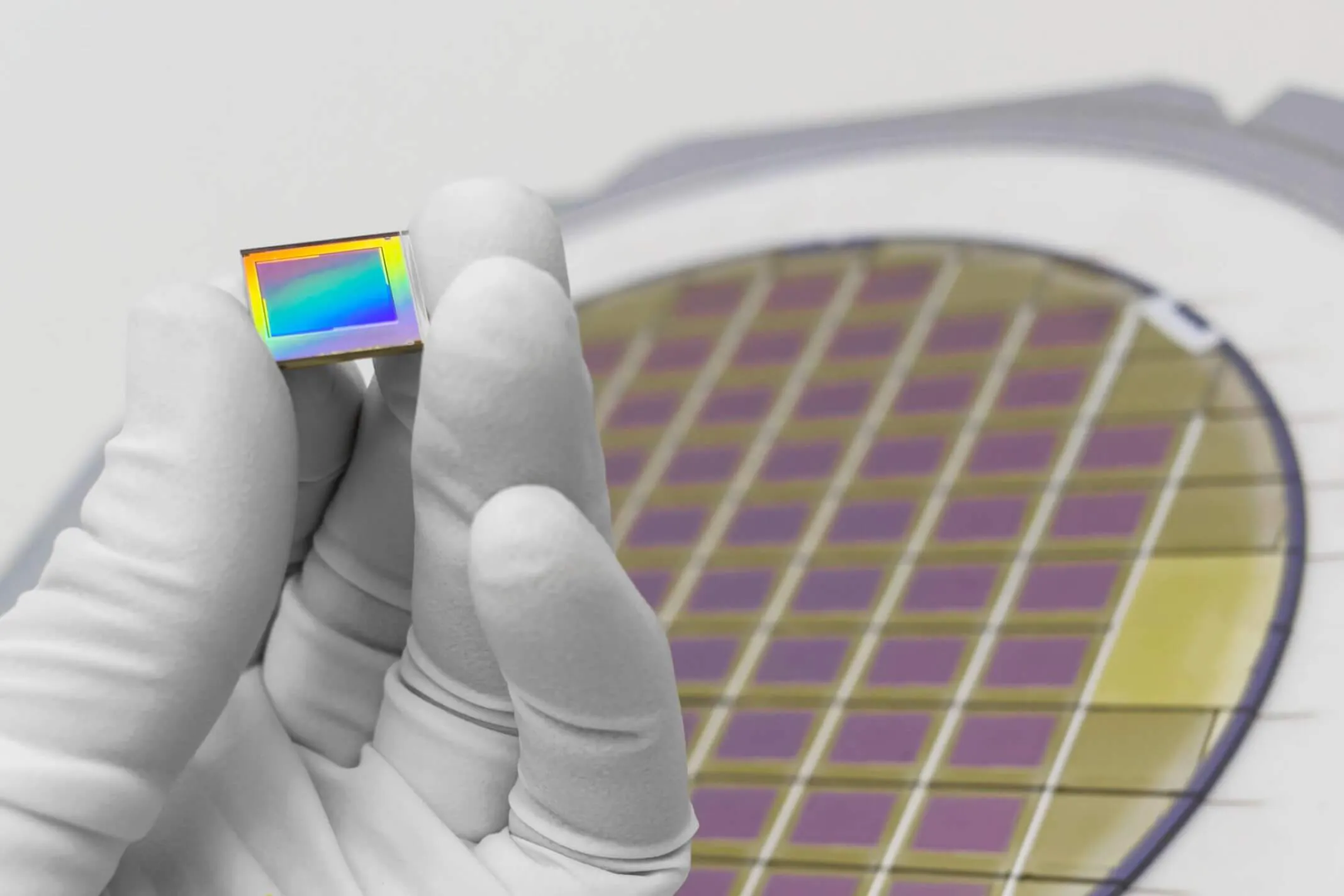システムエンジニアがやめとけと言われるのはなぜ?やりがいや向いている人も解説

システムエンジ�ニア(SE)という職業について調べていると、「きつい」「やめとけ」といったネガティブな声を目にすることがあります。確かに、長時間労働やプレッシャーの多さなど、この職業特有の厳しさが存在するのも事実です。
しかし、そうした声だけに惑わされて、システムエンジニアという職業の可能性を見過ごしてしまうのはもったいないかもしれません。なぜなら、SEには他の職業では得られない大きなやりがいや成長機会があり、適性のある人にとっては非常に魅力的なキャリアパスとなり得るからです。
本記事では、システムエンジニアが「きつい」と言われる理由を正直に解説するとともに、この仕事の本当の魅力や向いている人の特徴についても詳しくお伝えします。
システムエンジニアがきつい・やめとけと言われる理由はなぜ?
.jpg)
システムエンジニア(SE)がきついと言われる主な理由は、長時間労働になりやすい労働環境と精神的なプレッシャーにあります。特に、納期が迫るプロジェクト終盤や予期せぬトラブル発生時には、残業や休日出勤が増える傾向があります。
しかし、全てのSEが同じ環境で働いているわけではありません。自社開発企業や、労働環境の改善に積極的な企業では、これらの問題が少ない場合もあります。
納期に追われる
システム開発プロジェクトには厳密な納期が設定されていることが多く、計画通りに進まないことも珍しくありません。特に大規模なシステムや企業の基幹システムの場合、決められた期日までにリリースしなければ、クライアント企業の業務に大きな影響を与えてしまいます。
問題となるのは、予期せぬトラブルや顧客からの急な仕様変更が入った場合です。開発途中で「やっぱりここを変更してほしい」「新しい機能を追加したい」といった要求が出ると、それまでの作業計画が大幅に変更になることがあります。
しかし納期は変わらないため、納期に間に合わせるために残業や休日出勤が増え、激務になりやすいのが現実です。
トラブル対応を求められる
システムは常に安定して稼働しているとは限らず、エラーやバグが発生することは避けられません。特に本番環境でシステム障害が起きた場合、顧客の業務が停止してしまうため、一刻も早い復旧が求められます。このような緊急事態では、時間を問わず対応を求められることが多く、深夜や休日でも呼び出されることがあります。
また、原因の特定から復旧作業まで、限られた時間内で確実に問題を解決しなければならず、精神的にも大きなプレッシャーがかかります。一つのミスが大きな損失につながる可能性があるため、常に緊張感を持って業務に取り組む必要があります。
なお働きやすさの面では、近年リモートワークやフレックス制度を導入する企業も増えていますが、緊急時の対応が必要な性質上、完全に自由な働き方が難しい場合も多いのが実情です。
顧客と開発チームの板挟みになる
SEは、顧客の要望をヒアリングし、それを開発チームに伝えるという調整役を担うことが多く、時には顧客の無茶な要求と開発側の技術的制約や工数の事情の間に立たなければならない立場にあります。
顧客は「予算を変えずに、もっと高機能なシステムにしてほしい」「開発期間を短縮してほしい」といった要求を出すことがありますが、技術的に実現困難だったり、開発リソースが不足していたりすることがあります。
このような状況で、顧客の期待に応えつつ、開発チームの負担を軽減するバランスを取るのは容易ではなく、ストレスを感じやすい立場にあります。
技術の進化が早い
IT業界は技術の進歩が非常に速く、常に新しい知識や技術を学び続ける必要があります。プログラミング言語、フレームワーク、開発手法、クラウドサービスなど、あらゆる分野で新しい技術が次々と登場し、少し前まで主流だった技術がすぐに陳腐化することも珍しくありません。
このため、業務時間外での自己学習が欠かせず、プライベートの時間を使って新しい技術を習得したり、資格取得のための勉強をしたりする必要があります。学習を怠ると技術についていけなくなり、キャリアに影響する可能性もあるため、常に学び続けるプレッシャーを感じる人も多いのが実情です。
専門性が高い
システム開発には高度な専門知識が求められ、プログラミングスキルはもちろん、データベース設計、ネットワーク、セキュリティ、システム設計など、幅広い分野の深い理解が必要です。
さらに困難なのは、顧客の中にはITに関する知識が少ない人も多いため、複雑な技術的内容を相手に合わせて分かりやすく説明するコミュニケーション能力も求められることです。専門用語を使わずに技術的な制約や解決策を説明したり、非技術者でも理解できる形で提案書や報告書を作成したりするスキルが必要になります。
多重下請け構造になりやすい
日本のIT業界では、大手企業から中小企業へと何段階も案件が下請けに出される「多重下請け構造」が根強く残っています。この構造では、元請け、一次請け、二次請け、三次請けと段階が下がるほど報酬が少なくなる傾向があります。
実際の開発作業を担当するのは下位の下請け企業であることが多く、責任は重いものの報酬は限られているという状況が生まれがちです。結果として、仕事量と給料が見合わないと感じたり、スキルアップしても報酬に反映されにくかったりすることがあります。
客先常駐の働き方が合わない
SEの働き方として、自社ではなく顧客のオフィスに常駐して働くケースも多くあります。客先常駐では、プロジェクトごとに異なる環境で働くことになるため、その都度新しい職場環境や人間関係に適応する必要があります。
また、常駐先によって働き方や企業文化が大きく異なるため、環境の変化に柔軟に対応する能力が求められます。さらに、自社から離れて働くことで、自社での評価が見えにくかったり、キャリア形成の方向性が不明確になったりすることもあり、将来への不安を感じる人も少なくありません。
未経験だとシステムエンジニアは大変で難しい?
.jpg)
未経験からシステムエンジニア(SE)になるのは大変ですが、不可能なことではありません。特に、IT技術の学習には時間がかかり、実務では多くの課題に直面するため、独学や研修期間中に十分な準備をすることが重要です。
専門知識の多さ
SEに求められる知識の範囲は想像以上に広く、プログラミングスキルは入り口に過ぎません。実際の業務では、ネットワークの仕組み、データベース設計、セキュリティ対策、サーバー管理、クラウドサービスの活用など、IT分野の様々な専門知識を組み合わせてシステムを構築する必要があります。
特に未経験の場合、これらの基礎知識がない状態からスタートするため、一つひとつの概念を理解するのに時間がかかります。例えば、「APIって何?」「データベースの正規化とは?」といった基本的な用語から理解しなければならず、同期の経験者との知識差を埋めるだけでも相当な努力が必要です。
さらに、これらの知識は独立しているわけではなく、相互に関連し合っているため、体系的に理解するまでに長期間を要することが多いのです。
「未経験可」の言葉のギャップ
求人情報でよく見かける「未経験可」という文言には注意が必要です。多くの企業が「未経験可」と掲げていても、実際には「プログラミングの学習経験がある人」「ITパスポートや基本情報技術者試験などの基礎的な資格を持っている人」「独学でWebサイトやアプリを作ったことがある人」を想定していることが多いのが実情です。
完全にゼロからのスタートの場合、面接で基本的なIT用語について質問されても答えられなかったり、簡単なプログラミング課題が全くできなかったりして、企業が求めるレベルに達していない可能性があります。
「未経験可」だからと安心して応募しても、実際には一定の事前学習が前提となっているケースが多く、このギャップに戸惑う人は少なくありません。
自力での学習が難しい
プログラミング学習は、多くの人が途中で挫折しやすい分野として知られています。最初は基本的な文法を覚えることから始まりますが、実際にコードを書き始めると、エラーメッセージに悩まされたり、思ったように動作しないバグに遭遇したりすることが日常茶飯事です。
未経験者にとって特に困難なのは、問題に直面したときに自力で解決する力(いわゆる「ググる力」)を身につけることです。エラーメッセージの意味を理解し、適切なキーワードで検索して解決策を見つけ、それを自分のコードに適用するという一連の流れは、論理的思考力と根気強さが求められます。
また、コードが動かない原因を特定するデバッグスキルも、初心者には非常にハードルが高い技術です。
コミュニケーションの重要性
多くの人がSEの仕事を「パソコンに向かってコードを書く技術職」とイメージしがちですが、実際には顧客の要望をヒアリングしたり、開発チームとの調整を行ったりと、コミュニケーション能力が非常に重要な職種です。
顧客との打ち合わせでは、相手のビジネス課題を正確に把握し、それを技術的に解決可能な要求仕様に落とし込む必要があります。また、開発チーム内では、プログラマーやデザイナー、テスターなど様々な職種の人々と連携し、プロジェクトを円滑に進めるための調整力が求められます。
技術力だけでなく、相手の立場を理解し、分かりやすく説明し、時には難しい判断を伝える能力も必要となるため、未経験者にとっては技術習得と並行してコミュニケーションスキルも磨かなければならない点が大きな負担となります。
システムエンジニアとして働くやりがい
%20(2).jpg)
SEの仕事には、確かに大変な面も多いですが、それを上回る大きなやりがいがあります。ここでは、SEとして働く魅力や喜びについてご紹介します。
ゼロからモノを作り上げる達成感
SEの仕事の醍醐味は、顧客の漠然とした課題や要望をヒアリングし、それを具体的なシステムとして形にしていくクリエイティブな過程にあります。最初は「業務を効率化したい」「データを見やすくしたい」といった抽象的な要望しかない状態から、顧客と何度も対話を重ね、要求を整理し、技術的な解決策を考案していきます。
企画、設計、開発、テストという長い工程を経て、ついに一つのシステムが完成し、実際に顧客が使い始める瞬間は、何物にも代えがたい達成感があります。自分が設計した画面で顧客が作業をしている姿を見たり、「このシステムのおかげで仕事がやりやすくなった」という感謝の声を聞いたりするとき、SEとしての充実感を強く感じることができます。
まさに、無から有を生み出すクリエイターとしての喜びを味わえる職業です。
顧客や社会の課題を解決する喜び
システム開発は単にモノを作るだけでなく、顧客が抱える具体的な課題を解決するための手段です。例えば、手作業で行っていた煩雑な業務を自動化するシステムを開発すれば、顧客の残業時間を大幅に削減することにつながります。また、紙ベースで管理していた情報をデジタル化することで、情報共有の効率化や人的ミスの削減を実現できます。
医療機関の患者管理システムを開発すれば医療の質向上に貢献でき、教育機関の学習支援システムを作れば子どもたちの学習環境改善に役立ちます。このように、SEの仕事は直接的に人々の生活や働き方を改善し、社会全体に価値を提供できる職業です。自分の技術力が誰かの役に立っているという実感を得られることは、大きなモチベーションとなります。
常に新しい知識や技術を学べる楽しさ
IT業界の技術は日々進化しており、新しいプログラミング言語、クラウドサービス、AI技術などが次々と登場します。これは確かに学習の負担という側面もありますが、見方を変えれば「飽きることなく、新しいことに挑戦し続けられる」という大きなやりがいでもあります。
新しい技術を習得することで、これまで実現できなかった機能を開発できるようになったり、より効率的な解決方法を見つけられるようになったりします。例えば、AI技術を学ぶことで従来は人手に頼っていた作業を自動化できるようになったり、新しいフレームワークを覚えることで開発スピードが格段に向上したりします。
知的好奇心が旺盛で、学習することが苦にならない人にとっては、常に成長を実感できる非常に魅力的な環境と言えるでしょう。
チームで一つの目標に向かって進む一体感
システム開発は決して一人で完結する仕事ではありません。プロジェクトマネージャー、システムエンジニア、プログラマー、デザイナー、テスターなど、それぞれ異なる専門性を持つメンバーが協力して一つのシステムを作り上げていく共同作業です。
プロジェクトが進行する中で、メンバー同士が知恵を出し合い、困難な課題を乗り越えていく過程には、スポーツチームのような一体感があります。特に厳しいスケジュールの中で、チーム全員が同じ目標に向かって努力し、最終的にシステムが無事にリリースされたときの達成感は、個人の作業では味わえない特別なものです。
また、多様なバックグラウンドを持つメンバーとの協働を通じて、技術的なスキルだけでなく、チームワークや問題解決能力も自然と身につけることができます。
システムエンジニアに向いている人の特徴
.jpg)
一般的に「きつい」と言われるSEの仕事ですが、以下のような特徴を持つ人は、むしろやりがいを感じやすく、楽しく働けるでしょう。
論理的に物事を考えられる人
SEの仕事は、複雑な問題を分解して、一つひとつ順序立てて解決していく作業の繰り返しです。システム設計では「どのような順番で処理を行うか」「どこでエラーが発生する可能性があるか」といったことを論理的に考える必要があり、バグが発生した際も原因を特定するために段階的に検証していく思考力が求められます。
数学やパズル、プログラミングなどが好きな人は、この論理的思考力に長けていることが多く、SEの業務に自然に適応できる傾向があります。
知的好奇心が旺盛で、学習意欲が高い人
IT業界は技術の進化が非常に速く、常に新しい知識を学び続ける必要があります。今日使っている技術が数年後には古くなることも珍しくないため、継続的な学習は避けて通れません。
「新しい技術や知識に触れるのが楽しい」「知らないことを調べるのが苦にならない」という人は、この環境を負担ではなく刺激として捉え、SEの仕事を楽しむことができます。技術書を読んだり、新しいツールを試したりすることに興味を持てる人は、SEに向いていると言えるでしょう。
コミュニケーション能力が高い人
SEは一日中パソコンに向かっているイメージがあるかもしれませんが、実際には顧客、上司、同僚、外部ベンダーなど多くの人と関わる職業です。顧客の要望を正確にヒアリングし、それを開発チームに分かりやすく伝え、時には専門的な内容を非エンジニアにも理解できるように噛み砕いて説明する必要があります。
また、プロジェクトの進捗報告や課題の相談など、様々な場面で的確なコミュニケーションが求められるため、人と話すことが得意で、相手の立場に立って物事を考えられる人は、SEとして大きな強みを発揮できます。
地道な作業を苦にしない忍耐力がある人
システム開発には、エラーやバグの原因を何時間もかけて探したり、同じようなテスト作業を繰り返したりといった、華やかさのない地道な作業が多く含まれています。一見単純に見える機能でも、様々なパターンで動作テストを行ったり、想定外の操作でもシステムが正常に動作するかを確認したりする必要があります。
このような根気のいる作業を粘り強く続けられる忍耐力と集中力がある人は、品質の高いシステムを開発することができ、SEとして高く評価される傾向があります。
まとめ
システムエンジニアは確かに厳しい面もある職業ですが、適性のある人にとっては大きなやりがいと成長機会を提供してくれる魅力的な仕事です。重要なのは、現実を理解した上で自分に向いているかを冷静に判断することです。論理的思考力、学習意欲、コミュニケーション能力、忍耐力といった特徴を持つ人であれば、SEとして充実したキャリアを築くことができるでしょう。
システムエンジニアに興味をお持ちの方は、ぜひ当社のITS事業にご相談ください。経験豊富なエンジニアによるサポート体制と、一人ひとりの成長を重視した環境で、あなたのSEとしてのキャリアを全力でサポートいたします。未経験からでも安心してスタートできる研修制度も充実しています。